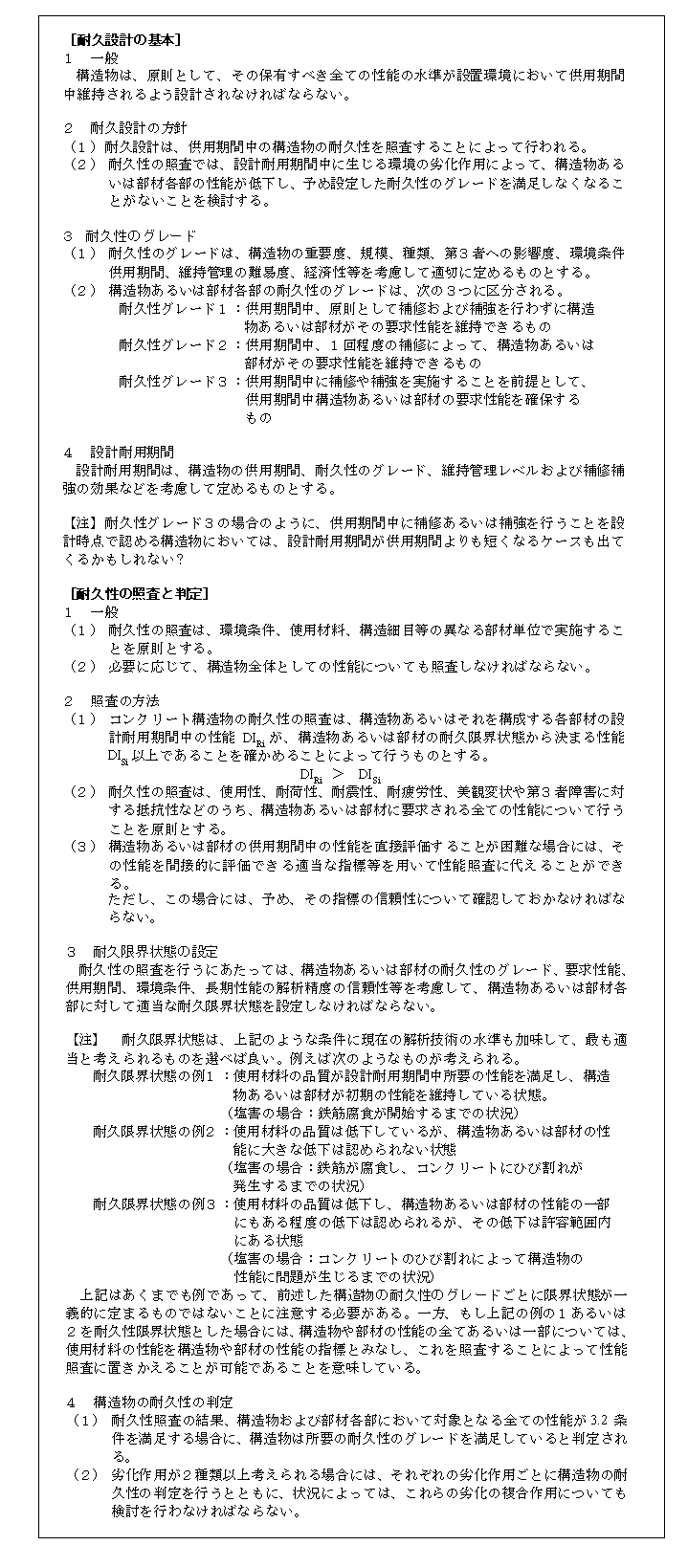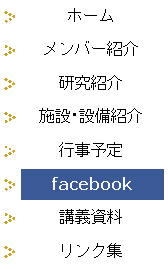
|
Concrete Laboratory |
|
塩害に対する耐久性を中心に考えたコンクリート構造物の長期品質 |
|
塩害劣化を理論的に予測するためには、以下フローに沿った研究が必要となる。 なお、研究の現状を色分けで示している。 |
|
1.塩害劣化現象とこれを予測するために必要とされる情報 |

|
(1)マクロ的アプローチ マクロ的アプローチの最も典型的なものは、土木学会編「コンクリート構造物の耐久設計指針(案)」であろう。この指針は、どうすれば耐久的な構造物が作製できるか、ということを中心に捉えてまとめられたものである。ただし、構造物の性能を直接評価するものではなく、その意味で、寿命予測的な評価指標とはなり得ない。
一方、最近、仕様規定型から性能規定型へ脱却のための一手法として、下記図のように耐久性関連の幾つかの試験を予め(あるいは施工中の)コンクリートに対して実施して、その結果の照査から構造物の長期性能を評価する方法が考えられる。このような考え方がマクロ的なものかどうかについては異論もあろうが、この場合も、構造物の性能を直接評価するものではないという点で、ここでは、マクロ的アプローチの分類に入れる。 |
|
2.塩害に対する性能照査方法に関する考え方 |
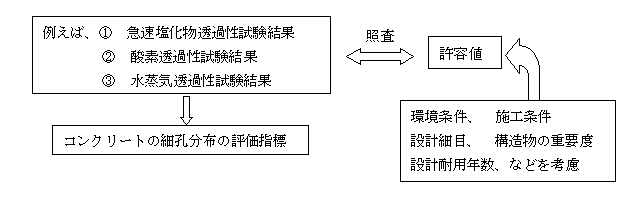
|
[利点] ・照査し易い ・鉄筋腐食に大きな影響を及ぼすコンクリートの物質移動性を評価できる ・鉄筋腐食開始までの期間を定性的に評価できる
[欠点] ・塩害評価としては定性的 ・環境条件、施工条件などと許容値の関係を一義的に定めることが難しい ・維持管理と連動した指標とはならない ・鉄筋腐食開始後の評価指標とはならない |
|
(2)メゾ的アプローチ 基本的には、前項の1.に示した塩害劣化解析のフローに従って、構造物の塩害による劣化状況を推定し、これを基にした指標により耐久性を評価する方法である。ただし、コンクリートの品質や環境条件が劣化過程に与える影響に関する解析用値は、主に既往の調査ならびに実験データを用いるため、完全な理論解析とはならず、劣化解析の不確実性については個々に安全係数を設定して対応しなければならない点や、現状では解析が困難なところについては基本仕様を設定する必要がある点など、マクロとミクロの中間的なアプローチの方法となる。
その1つの考え方の例を次のフローで示す。 |
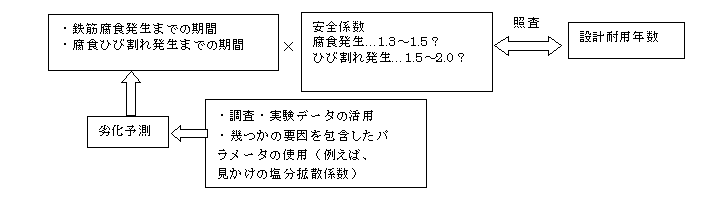
|
[利点] ・耐用年数を直接評価でき、照査の意味が明確 ・維持管理計画と連動できる ・腐食ひび割れ開始時期まで検討できる ・今後の研究成果を直接取り込むことができる
[欠点] ・安全係数の取り方によって、評価がどのようにでもなり得る ・現状では、ある程度の基本仕様の設定が必要 ・算定に手間が掛かる |
|
(3)ミクロ的アプローチ 前頁の1.に示したフローに従って、厳密な解析を行って、構造物の設計供用期間中の状態を求め、これを構造物に要求される性能と比較し、照査するものである。ただ、実際には、コンクリート中の物質移動と物質反応などをミクロモデルを用いて理論的に評価し、しかも実状に即した解を得るには、かなりの無理があるものと考えられる。したがって、当面は、メゾモデルを徐々により詳細な評価が可能なモデルに改良していくことをミクロ的アプローチとすべきであろう。
ミクロ的アプローチの流れの一例を下記に示す。 |

|
構造物の長期品質を照査するということは、本質的には、構造物に要求される諸性能が供用期間中満足していることを確認することである。一方、耐久設計は、広義には長期品質を照査することと同義語となるが、一般的には、構造物の各要求性能ごとにその長期性能変化の状況を把握することが困難なため、それらの構造物の長期性能を耐久性という枠で括って、ある程度総合的に評価しようとすることと捉えられている。 その意味では、劣化現象に対するメゾ的アプローチの範囲では、コンクリート構造物の長期品質照査は耐久設計の枠組みの中で行っても大きな差は生じないものと考えられる。しかし、今後、構造物に要求される性能についてその長期性能変化の状況が明らかになってくると、その明らかになった性能に対しては、その長期性能について個々に照査を行い、最終的には耐久性という枠組みで括って評価する必要はなくなるものと思われる。 ただ、それでも、構造物によっては、照査の簡便性、各性能の評価の限界、あるいは維持管理計画との兼ね合いなどにより、耐久性という枠組みで照査した方が良いとする状況は残るものと思われる。このようなことを考慮して、近未来からある程度先の未来まで共通して適用できる耐久設計の概念を現時点でしっかりと構築しておく必要があるものと考えた。ここでは、これまでの塩害研究の成果と今後の動向を念頭において、その一案を未だ大枠ではあるが提示することにした。
その設計の流れを下図に示す。 |
|
3.近い将来における長期品質照査(耐久設計)に関する一提案 |
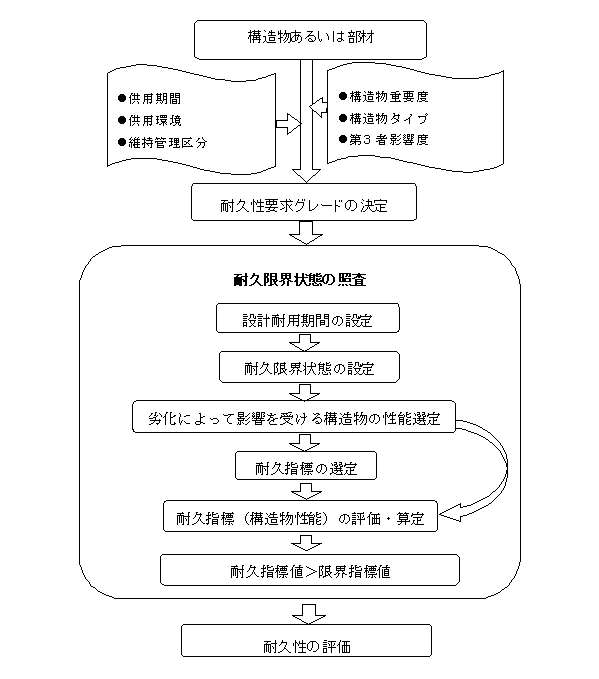
|
また、上記の設計の流れを基にして考えられる具体的な設計方針の一例を以下に示す。 |