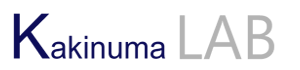気圧変動と長周期波
Long Waves Generated by
Atmospheric Pressure variation
長周期波とは,
どういう波でしょう.
長周期波とは,周期の,あるいは,波長の長い波っす.
気圧変動に伴う
長周期波の数値解析 #1
2009年2月24日〜26日に,九州地方の広範囲で湾水振動を伴う比較的大きな潮位変動が発生し,鹿児島県上甑島(かみこしきじま)浦内湾湾奥の小島漁港では,船舶の転覆,家屋の床下浸水や,堤防の破損が生じました. このような被害を未然に防ぐためには,各湾において発生する長周期波の特性を把握し,港の設計や,各種施設の設置時に考慮しておくことが要求されます.
こうした湾水振動は,外洋より伝播した波列が湾内に入射し,ある周期の長周期波成分が湾内で選択的に増幅されることによって発生します. ところで,湾水振動が生じるような周期の長周期波が湾に入射しても,その継続時間が短ければ,湾水振動は,高潮位を示すほど発達することなく減衰するでしょう.
すなわち,現地の湾で顕著な湾水振動が発生したとき,湾の固有周期に近い長周期波が,十分な数の波からなる波列として湾に入射したと考えられます. 湾内の大きな振動は,入射波の周期,振幅,そして,継続時間に依存して発生するのです. 長周期波が外洋より入射する原因の一つとして,外洋における海上の微気圧変動に伴う長周期波の発生が考えられています. そこで,本研究では,九州西岸域の湾における湾水振動が,外洋上における気圧変動域の移動に伴う長周期波の入射によって発生すると仮定します. そして,気圧変動域の移動に伴う長周期波発生過程の数値解析を行ない,上甑島浦内湾内に高い増幅率が現れるような周期の長周期波が東シナ海で発生し得るのかに関して調べます.
気圧変動に伴う
長周期波の数値解析 #2
九州西岸域では,2〜4月にかけて「あびき」と呼ばれる潮位副振動が頻繁に観測されます. 2009年2月24日〜26日に,九州西岸域の広範囲であびきが生じた際には,鹿児島県と熊本県において,船舶の転覆や床上・床下浸水等の被害が発生し,鹿児島県上甑島(かみこしきじま)の浦内湾の湾奥に位置する上甑町瀬上地区の小島漁港では,全振幅が3mにも達する水位変動が確認されています. また,2本に分岐した湾形を有する浦内湾の分岐部に設置されたマグロ養殖の大型生簀も破損被害を受けましたが,これは,あびきに伴う大きな流速によると考えられます. こうしたあびきは,湾の「固有周期」付近の周期を有する長周期波成分が各湾に入射するために発生しますが,そのような長周期波が外洋で生成する原因の一つとして,海上における気圧の擾乱が挙げられます.
ところで,ある湾内であびきが大きく成長するためには,その湾の固有周期に近い周期の成分が,外洋において比較的大きなエネルギーを有して湾に入射すること,そして,そうした長周期波が,湾内で減衰してしまう前に継続して入射することが必要です. 前者に対しては,気圧変動の偏差の絶対値と,気圧波の移動速度が長周期波の波速に近い場合に生じる「共鳴作用」とが関与するでしょう. 他方,後者の原因としては,地形に起因する反射といった何らかの機構により,入射波が複数波となることが挙げられます.
そこで,本研究では,あびきを増大させる可能性のあるこれら二つの原因に着目して,東シナ海上の気圧変動に伴う長周期波の発生・伝播過程の数値解析を行ない,浦内湾におけるあびきの生成要因に関して調べました.